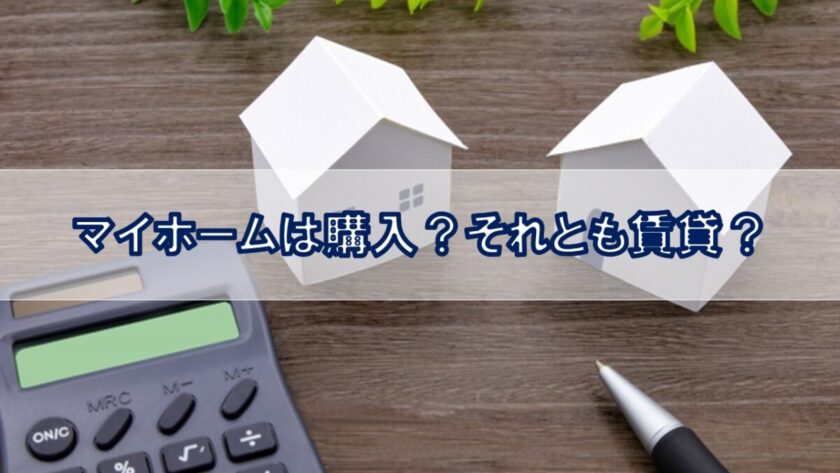「マイホームを購入すべきか、それとも賃貸のままが良いのか?」
誰もが一度は悩むこの問い。特に現在、東京の不動産価格が高騰している2025年においては、その判断は一層難しくなっています。
私の身近な例でも、賃貸の更新時に家賃が上がることに直面し、マイホーム取得を考え始める方が増えています。しかし、具体的な住宅ローンの返済額や期間の長さを知ると、「長期間こんなに払い続けられるだろうか」と不安を抱くのも無理はありません。
そこで今回は、東京の現状を踏まえ、購入と賃貸のメリット・デメリットを徹底比較し、後悔しない選択をするためのポイントを解説します。
2025年現在の東京の不動産市場と金利動向
まず、現在の市場環境を整理しましょう。
1. 東京の不動産価格は「高止まり」または「上昇基調」
2025年現在、特に東京23区内の新築・中古マンション価格は、過去最高水準で推移しています。
- 要因1:建築コストの高騰 – 資材費や人件費の高騰が新築価格を押し上げています。
- 要因2:需要の堅調 – 都心回帰の傾向、再開発エリアへの注目、さらに円安の影響もあり、海外投資家からの需要も高まっています。
- 傾向:二極化の進行 – 都心部や駅近の資産価値の高い物件は高止まり、または上昇傾向が続く一方、郊外や築古物件では価格が二極化するリスクがあります。
この高騰市場において、購入のハードルは上がっていると言えます。
2. 住宅ローン金利は「上昇傾向」
長らく続いた低金利時代が終焉を迎えつつあり、特に固定金利は上昇傾向が顕著です。
- 固定金利:全期間固定型である【フラット35】などは長期金利の上昇を受け、金利が上がっています。
- 変動金利:現時点では比較的低水準を維持していますが、日銀の追加利上げ観測などから、将来的な上昇リスクが高まっています。
住宅ローンの返済期間は長期にわたるため、金利の上昇は総返済額に大きく影響します。特に「長期間払い続けられるか」という不安は、この金利環境を背景にしたものです。繰り上げ返済による期間短縮は、金利上昇リスクを軽減する有効な手段となり得ます。
マイホーム購入(持ち家)のメリット・デメリット
高騰する東京でマイホームを購入する際の具体的なメリット・デメリットを見ていきましょう。
| 持ち家のメリット | 東京で購入する場合の補足(2025年) |
| ① 生涯の安心感と自由 | 終の棲家を確保でき、リフォームやリノベーションも自由にできます。 |
| ② 資産形成になる | 東京の都心部や好立地物件は、価格高騰の恩恵を受けやすく、資産価値が維持されやすい傾向にあります。将来、貸し出す(賃貸に出す)ことで家賃収入を得ることも可能です。 |
| ③ リバースモーゲージ | 条件によりますが、老後に自宅を担保に生活資金を得る「リバースモーゲージ」制度を利用できる可能性があり、老後の資金計画の選択肢になります。 |
| 持ち家のデメリット | 東京で購入する場合の補足(2025年) |
| ① 初期費用と維持費の負担 | 高騰した物件価格に加え、諸費用(頭金・仲介手数料・税金など)が重くのしかかります。また、月々のローン返済以外に、固定資産税・火災保険料・修繕積立金(マンションの場合)などの維持費がかかり続けます。 |
| ② 流動性リスク | 売却して住み替えたいと思っても、希望の価格で売れるとは限りません。特にエリアや築年数によっては、不動産価格の二極化により売却が難しくなるリスクもあります。 |
| ③ 選択による費用変動 | 新築か中古か、マンションか戸建てかによって、取得費用や維持費が大きく変わり、慎重な検討が必要です。 |
賃貸のメリット・デメリット
不動産価格が高騰している今だからこそ、賃貸のメリットも再評価されています。
| 賃貸のメリット | 東京で賃貸の場合の補足(2025年) |
| ① まとまった資金が不要 | 購入のような高額な初期費用(頭金など)は不要です。敷金・礼金などの初期費用も、購入の初期費用に比べれば少額です。 |
| ② ライフスタイルに合わせた住み替え | 家族構成や勤務地の変化に合わせて、比較的簡単に住み替えができます。高騰する不動産を購入する「決断の先送り」ができるのもメリットです。 |
| ③ 柔軟な対応力 | 災害などの突発的な事情にも柔軟に対応でき、家の維持管理は大家や管理会社が行うため、手間や費用負担がありません。 |
| 賃貸のデメリット | 東京で賃貸の場合の補足(2025年) |
| ① 家賃は資産として残らない | 毎月の家賃は大家の収益となり、自身に資産として蓄積されることはありません。また、家を自由にリフォームすることも基本的にできません。 |
| ② 更新料・家賃上昇リスク | 賃貸更新時に更新費用がかかるほか、不動産価格の上昇に伴い、家賃も上昇するリスクがあります。これがマイホーム検討のきっかけになるケースも多いです。 |
| ③ 高齢時のリスク | 高齢になると、保証人や入居審査の関係で新たに部屋を借りにくくなる場合があります。将来的に高齢者向け住宅や介護施設への入居も視野に入れ、資金計画を立てる必要があります。 |
まとめ:納得できる選択のために
このように、購入・賃貸それぞれにメリット・デメリットがあり、特に不動産価格が高騰し、金利が上昇傾向にある2025年の東京においては、どちらが得かという判断は一層複雑です。
重要なのは、「キャッシュフローの安定性」と「心理的な納得感」です。
- ライフプランとキャッシュフローの作成: 住宅ローンは長期にわたります。購入後も、教育費や老後資金、仕事や家族の変化に伴う出費に対応できるよう、身の丈に合った具体的なライフプランとキャッシュフロー表を作成し、定期的に更新して将来を見通すことが極めて大切です。繰り上げ返済計画もその一部として検討しましょう。
- 資産価値の検討: 購入する場合は、単に「今の住みやすさ」だけでなく、立地や物件の特性(新築/中古、マンション/戸建てなど)を鑑み、将来の資産価値が維持されやすいかを冷静に判断することが重要です。
- 心理的な負担の有無: 購入にせよ賃貸にせよ、毎月の支払いが「心理的な負担」とならないような選択をすることが、何よりも重要です。
不安や疑問を抱えたまま進めるのではなく、専門家とも相談しながら、ご自身とご家族が納得できる選択を心がけましょう。
住宅購入は、お客様のライフプランや目的によって、ご提案もことなります。
おうちの相談カウンターでは、住宅購入について無料でご相談できます。
お気軽にご相談ください。
#賃貸
#購入
#売買
#2025
#不動産
#おうちの相談カウンター
#マイホーム
#メリット
#デメリット
#金利